
.jpg)
行動食は登山の基本でありながら、そこそこ奥が深い分野でもあると思っています。
この記事では、登山における行動食について、「基本的な考え方」と「実際の私の行動食」の二部構成でご紹介させて頂きます。
目次
【登山歴7年】行動食の選び方とカロリー計算方法「夏山~冬山/日帰り~テント泊」
行動食と水分量の基本「必要量と計算方法」
行動食の必要なカロリー量
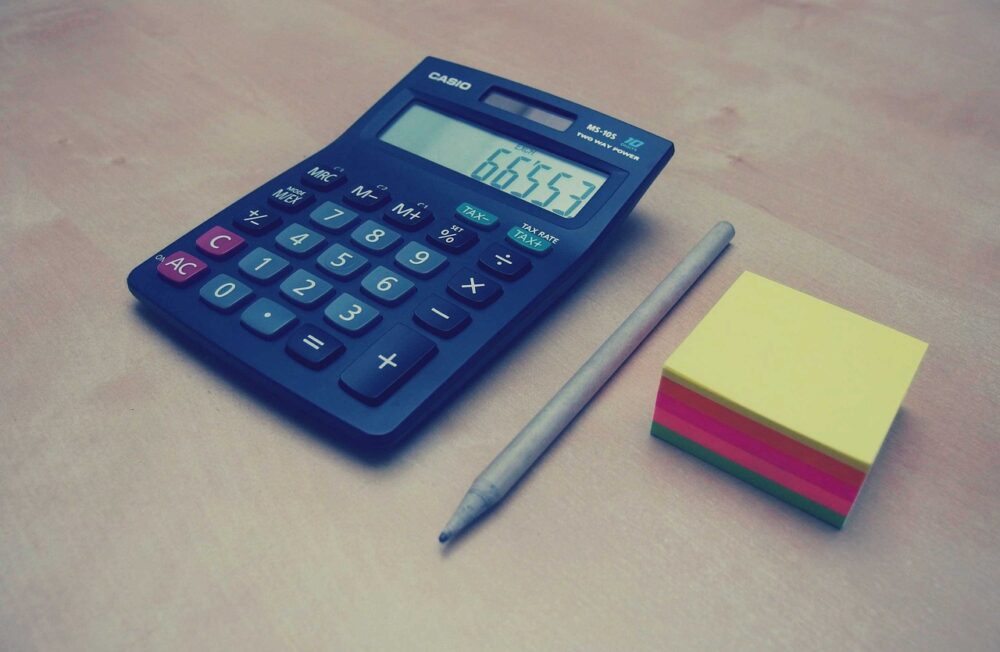
行動食の量は「なんとなく、このくらい?」と決めるのではなく、登山で消費されるカロリーから逆算して行動食の量を算出します。
登山で消費されるカロリーは、以下の計算式から出すことができます。
登山1日の消費カロリー
「体重+装備重量(kg)」×「5kcal(固定値)」×「行動時間」+「基礎代謝量」=消費カロリー
※消費カロリーを算出する計算式は数種類ありますが、どれを使っても大体同じ数値となります。
実際の例題をもとに計算方法を見て行ってみましょう。
《例:1泊2日のテント泊に行く場合》
- 体重:67㎏
- 装備:15kg
- 基礎代謝:1600kcal
- 行動時間:1日目6時間、2日目8時間
【1日目】「体重67kg+装備15kg」×「5kcal」×「行動6時間」+「基礎代謝1600」
=4060kcal
【2日目】「体重67kg+装備15kg」×「5kcal」×「行動8時間」+「基礎代謝1600」
=4880kcal
2日間の合計で約9,000kcal分のエネルギーが必要ということになります。
では9,000kcalの相当量を食事に換算すると、、、
- オニギリ、45個分(1個:200kcal)
- ソイジョイ、112本分(1本:80kcal)
- チョコバー、50本分(1本:180kcal)
- ふるぐら、2.2kg(100g:400kcal)
えっ、めちゃくちゃ多い、こんなに山に持っていけないとなりますよね。
当然です。
9,000kcalの中には、
- 登山前の朝食
- テントでの食事(夕食/朝食)
- 体内の脂肪を消費してエネルギーへと変換する換算値
の3つが含まれています。
【1】と【2】の朝や夜の食事はご存知の方も多いとは思いますが、【3】の体内の脂肪も消費して行動中のエネルギーへと変換されているというご存知でしょうか?

脂質代謝型歩行法といって適切な心拍数を保った歩行をすることで、体内の脂肪をエネルギーへと変換しながら歩くので、自分自身の肉体を効率的に使用する事が出来ます。
上手くいけば、消費カロリーの約半分を脂肪から賄う事が出来ると言われています。
≪適正な心拍数の計算式≫
・220(固定値)-年齢 =最大心拍数
・最大心拍数 × 60%~70% =適正心拍数
【例】30歳の場合
220(固定値)-30歳 =190(最大心拍数)
190 × 60%~70% =適正心拍数114~133
これらを踏まえて、2日間の食事メニューを割り振ってみると、
≪1日目≫
朝食:出発前に800kcal摂取
昼食:行動食で1,350kcal摂取
夕食:テントで500kcal摂取
≪2日目≫
朝食:テントで500kcal摂取
昼食:行動食で1,350kcal摂取
総合計:4500kcal摂取
こうなると、大分と現実的な数値になりますね。
行動食と非常食は別です
稀に「行動食」と「非常食」を一緒にしている人がいますが、これは良くありません。
【行動食】行動する為に補給する栄養であり、下山時に食べきっても良い物。
【非常食】緊急時に「救助される迄に生き伸びる為の食料」であり、必ずザックには忍ばせておきますが通常は食べません。
どんなに小さな山であっても、必ず非常食は携帯しましょう。
水の量

行動食と同じで、水分量に関しても必要量を算出する計算式があります。
登山1日の消費水分量
「体重(kg)」×「5g(固定値)」×「行動時間」×「80%(固定値)」=消費水分量
これに加えて、調理をする場合は調理用の水分、そして緊急時の備蓄用(500ml)の常時携帯が推奨されています。
《例:1泊2日のテント泊に行く場合》
- 体重:60㎏
- 装備:15kg
- 行動時間:1日目6時間、2日目8時間
▼消費分
1日目:「体重60kg」×「5g(固定値)」×「行動6時間」×「80%(固定値)」=1440ml
2日目:「体重60kg」×「5g(固定値)」×「行動8時間」×「80%(固定値)」=1920ml
▼調理分
1日目(夕食):フリーズドライ150ml、ラーメン200ml
2日目(朝食):フリーズドライ150ml、ラーメン200ml
▼常備分
500ml
総合計:4,560ml
因みに、浄水器を携帯していれば、沢の水も安心して飲むことが出来るので、携帯する水の量を減らす事ができます。
おすすめ&実際の行動食

それでは、私の実際の山の中での行動食や食事メニューをご紹介します。
行動食

行動食を選ぶ際は、「糖質」「ビタミン」「ミネラル」などの栄養成分や、消化吸収など考えるべきポイントは沢山ありますが、「食べやすさ」もとても大切です。最初のうちは「自分が美味しい」と感じものを選ぶと良いでしょう。
以下は私が実際に使用している行動食を中心にご紹介していきます。
- チョコバー
「ソイジョイ」「カロリーメイト」「一本満足バー」などが有名でしょうか。様々な栄養素が含まれていながら美味しくて、サクッと短時間で補給できるので、岩稜登山などの危険を伴う山行でもスピーディーに摂取できるので、個人的にもお勧めです。但し、チョコ系は夏の時期は溶ける恐れがありますが、ソイジョイはオールシーズン活用しています。
- ナッツ系
ナッツにはビタミンやミネラルが豊富に含まれており、体力の持続性に大きな働きをしてくれると言われています。
チョコレートは瞬発的に体力を回復させますが、直ぐに下降すると言われているので、チョコとナッツのハイブリット型のお菓子がおすすめです。
個人的にはアーモンドと小魚な一緒になっている「アーモンドフィッシュ系」がおすすめです。量と価格を考えると決して安くはありませんが、懐かしい感じがして個人的に好きです。 - ふるぐら・グラノーラ
豊富な栄養素と高カロリー、ぽりぽりとした触感、高温~低温下でも品質に変化が無いので、オールシーズン利用可能で非常にお勧めの行動食です。
色々な種類が販売されているので、好みのメーカーを見つける楽しみもあります。 - ゼリー系・アミノバイタル
≪ゼリータイプ≫
ゼリーという飲みやすさで、栄養と同時に水分も摂取できるのがお勧めポイントです。冬は凍結の恐れや体温低下の観点から使用出来ませんが、夏場のアプローチなど、身体が山に順応しきっていないタイミングで摂取すると非常に効果がある印象です。
販売されている商品としては「アミノバイタル」や「ウィダーinゼリー」などが有名ですが、「ガッツギア」などでも効果は大きく変わらないように思うので、予算と気分で決めています。≪顆粒タイプ≫
顆粒タイプのアミノ酸は、ゼリー以上に有名なのでご存知の方が殆どだと思います。ここでは細かい説明は省略しますが、アミノ酸が運動中に身体にとって大切であるという事は科学的根拠もあるようです。
個人的に効果を実感しているので、大きな山行の時は、朝昼晩、各1本ずつ飲んでいます。
飲んだら疲れ知らずというような事は起こりませんが、「底力に差が生まれる」といった印象で、効果はあると思います。
これは店頭よりもネットの方が安いですので、楽天やAmazonで購入するようにしています。 - ドライフルーツ
果物に含まれる天然の糖分は、体内への吸収も良く、ビタミンなどの栄養素も豊富で登山では人気の行動食の一つです。乾燥されているので夏場でも腐敗や変形がしにくいのが利点です。
私は最近は「イモけんぴ」にハマっています。ポリポリとした触感が疲れた身体でも無理なく食べる事が出来ます。 - おにぎり
保存性を除けば、これが一番効果が高いと思います。糖質、塩分、ミネラル、でんぷん等、登山に必要とされる栄養素を豊富に含んでいながら、普段から日常生活で摂取している食材なので身体での対応も良く、効率的に栄養へと変換できると感じています。夏は腐敗の恐れ、冬は凍結の恐れがあるので、春や秋の日帰り登山などにお勧めです。
食事・食料
出発前の朝食

朝食と夕食はしっかりと食べる事ができる貴重な時間ですので、しっかりと栄養補給をしておくべきです。
朝は時間が沢山は取れないので、おにぎりや菓子パンなどの直ぐに食べられるもので済ますと良いでしょう。
個人的にはパンよりも米の方が腹持ち良いという印象ですが、これは体質などの個人差があるので、ある程度は柔軟に考えても良いと思います。
ポイントとしてはしっかりと食べるという所にあります。
日帰り登山での昼食
.jpg)
.jpg)
日帰り登山に関しては、山行の種類により違います。
「日帰り遠征」や「日帰りロング山行」などの場合は、計算方法や食料の選定はテント泊の時と大体同じで、しっかりとした食糧計画を立てていますが、
歩行い時間が5時間以内で、装備重量も5㎏以内などの軽度のハイキングの場合は、菓子パンなどの比較的安価な物で済ます場合が多いです。
目安として「150kcal」×「休憩の回数」としています。
この場合、計算式から算出される数値から見ると全然足りていませんが、身体への負荷も低い為、これで足りていますが、これは自分自身の経験から導き出している答えとなります。
テント泊での夕食

夕食は腰を据えて食べる事ができるので、1日目の疲れを翌日に持ち越さない為にも、しっかりと栄養補給をしなければいけません。
山荘の食事を利用する場合は献立で特に悩む必要はありませんが、テント泊などで自炊の場合は、「食べたい物でOK」です。
食材を持ち込んで「○○鍋」等といった本格的な調理も良いですし、お湯を注ぐフリーズドライやインスタントラーメンなどでも問題ありません。
こちらもポイントとしてはしっかりと食べるという所にあります。

また、最近はインスタントラーメンではなく、カップラーメンを食べ終わったフリーズドライの復路に入れてお湯を注いで食べています。
クッカーでラーメンを作らない理由は2つあります。
【理由1】時間を短縮
クッカーの湯沸かしが終われば、直ぐに片づけられる。
【理由2】クッカーが汚れない
冬季はクッカーで雪を溶かして飲料水を作るので、飲料水に油が浮いているのが個人的に嫌。
因みに、どうでも良い話ですが、日清のカップヌードルのリフィルも便利ではありますが、どうせ中身をジップロックに入れ替えて持って行くので、割高のリフィルを選ぶ必要は無いと思います。
具体的な摂取カロリー
テント泊

これは2月の西穂高岳西尾根(1泊2日)の実際の食事と行動食のメニューとなります。
※写真は2人分、記載のメニューは1人分となります。
≪行動食(2日分)≫
・ふるぐら(350g/計1533kcal)
・ナッツ&煮干し(45g/計150kcal)
・ソイジョイ(6本/計480kcal)
・ココア(6本/計306kcal)
・アミノバイタル顆粒(3本/計51kcal)
行動食 総カロリー:1,232kcal
≪食事≫
【1日目】
朝:コンビニのおにぎり(3個/計600kcal)
夜:ラーメン(1.5人前/計633kcal)、フリーズドライ(0.5人前/計183kcal)
【2日目】
朝:ラーメン(1.5人前/計422kcal)、フリーズドライ(1人前/計366kcal)
食事 総カロリー:2,204kcal
総摂取カロリー:4724kcal
計算式と照らし合わせてみましょう。
《私の場合》
- 体重:58㎏
- 装備:20kg
- 基礎代謝:1500kcal
- 行動時間:1日目8時間、2日目09時間
1日目:「体重58kg+装備20kg」×「5kcal」×「行動8時間」+「基礎代謝1500」=4,620kcal
2日目:「体重58kg+装備20kg」×「5kcal」×「行動9時間」+「基礎代謝1500」=5,010kcal
合計9,630kcal分のエネルギーが必要ということになります。
この内の半分(4815kcal)を食事から摂取するという事ですので、凡そ計算通りの内容で出来ていると言えるでしょう。
【補足】理想と現実「飽きと加齢による味の変化について」
ここまで行動食の量や内容について話してきましたが、実際には正論通りに行かないことも良くあります。
登山を長く続けていると、以前食べられていた物が喉を通らなくなってくる事があります。
私自身もそうです。私は現在30代で、登山を開始して7年以上が経過して、食事内容が定着しているようで、常に試行錯誤の連続です。
飽き
登山を開始した頃は、何を食べても美味しいです。
お湯を注いで熱々のご飯が完成するフリーズドライなんか、感動して色々な味を試していました。
その頃は「フリーズドライは不味くて喉が通らない」と言っている人のSNSを読むと「なんて贅沢な人だ」と怒りを覚えるくらいでした。
でも、登山を開始して6年くらいが経過して、テント泊の数もそれなりに増えてくると、味に対しての新鮮味がなくなり、どうしても「飽き」を感じてしまう事は否定できません。
フリーズドライは各社から数多くの「味」が販売されていますが、長く続ければ続ける程、「食べたい味」と「食べたくない味」が決まってくる為、必然的に選ぶ種類は固定化されくるのと、「フリーズドライ」という加工食品は味に変化がない為に「飽き」はある程度は避けられないものだと思います。
加齢による体調の変化
私自身、現在30代で登山の世界ではまだまだ若い方だとは思いますが、それでも20代の頃に比べると消化能力の低下を感じています。
自身20代の頃は遠征時は、前日の夕食は餃子3人前、朝食は牛丼など、とにかくカロリーを大量に摂取して登山に向かっていました。それでパワーマックスで山頂まで登れていました。しかし、30代に突入してからは、登山の前は消化の良いものの方が、山に入ってからのコンディションが良い傾向にあります。
山の中での食事も然りで、以前は行動食やテント内での食事内容がカロリー保有量をメインで選んでいましたが、最近は必要なカロリー量をクリアする条件で、栄養素や消化効率、自身の身体への適応度合いで選ぶようになってきています。
味ではなく栄養補給へ
そもそもが、山の中での食事が「目的」なのか「手段」なのかで大きく変わってきます。
「食事」は目的の山行を達成する為のプロセスの一つでしかなく、ただただ栄養補給として口の中に放り込むという「作業」と化してくる現実もあります。
食事内容が山行の成功決めると言っても過言ではない為、これまでの経験を元に行動食や食事内容を決めていきます
- これまで得た知識を元に、栄養素や必要カロリー量など決める。
- 季節や行程、歩行する場所がどんな場所なのかによって、行動食の内容を決める。
- 自身の体調を振り返って、いつ何をどのくらい食べられば、摂取したカロリーが身体に順応するのか。
などなど、色々と考えて決めていきますが、これらは、登山の醍醐味でもあります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
「行動食や水分量」の基本的な考え方についてご紹介させていただきました。
しかし、これは基本であって絶対ではありません。
- 少量で問題ない人
- 全然足りない人
- 加工食品が苦手な人
など、人によって違います。
また、しっかりと食べれば体力は回復しますが、その分荷物の重量が増して体力も削られます。
だからと言って、ギリギリの内容で攻めると、想定以上に食料を消耗した際に対応出来ません。
この様に行動食の選定は、意外と奥が深いものです。
ポイント
基本事項を踏まえた上で、試行錯誤を繰り返して、自分のスタイルを見つけていく
というのが理想の行動食へと繋がっていきます。
最後にアドバイスをするならば、最初の内は「美味しさ」を重視される事をおすすめします。
ただでさえ苦しい登山です。口にする物くらい好きな物を食べましょう。
ストイックにするのはステップアップをする時で十分間にあいます。
関連記事
- 実際に遭遇したヤバい連中「夏山前編・後編」「雪山編」「クライミング編」「バリエーションルート」「登山ショップ編」「講習会編」
- 成長しない登山者の特徴【初級編】【中級編】
- 【徹底解説】雪山登山に必要な全装備を紹介「日帰り~テント泊」
- 【徹底解説】初めての登山用「山岳テント」の選び方